授業についていけない原因は?小・中・特性別の対処法と親の関わり方
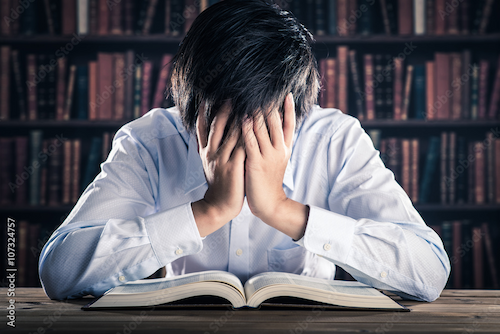
「うちの子、最近授業についていけていないみたい…」
そんなふうに感じると、親御さんとしてはとても心配ですよね。
授業についていけない原因は一つではありません。年齢によっても、子どもの特性によっても違ってくるので、それぞれの対処法が必要となります。
そこでこの記事では、授業についていけない原因を年齢別・特性別にわかりやすく解説し、親御さんができるサポート方法も紹介していきます。
お子さんの成績に不安を感じていませんか?
家庭教師のゴーイングには、勉強が苦手なお子さんや不登校・発達障害のお子さんを成績アップに導いてきた経験豊富な先生が揃っています。
ぜひ、ゴーイングのホームページでお住まいのエリアで活躍中の先生をチェックしてみてください!
授業についていけない…それってどんな状態?
親御さんも授業についていけなかった経験があるかも知れませんが、もうその感覚を忘れてしまいましたよね。
ですが、お子さんの悩みを理解してあげるために、ちょっとだけ昔を思い出して欲しいです。
「授業についていけない」というのは、例えば次のような状態を指します。
• 授業中、先生の話が頭に入ってこない
• ノートをとるのが間に合わない
• 黒板を写すのに時間がかかり、話に置いていかれる
• 宿題すら何を出されたのか分からない
• テストの点が極端に下がっていく
この他にも、「その場では理解しているように見えても、後でわからなくなる」というケースも多いです。これは宿題を真面目にやれば、家でその日のうちに気づけることなので、親御さんは注意して見てあげてください。
小・中・特性別に見る「授業についていけない」原因
小学生・中学生・発達障害の子の代表的な悩みを紹介していきます。ここにあげた項目は、本当にありがちなことなので、逆に見落としがちになり、「誰でもそうだよね」などとその場で流してしまうこともあります。
ですが、初期段階で「勉強のつまづき」に気づいてあげられれば、遅れは最小限で済むので、できるだけ気をくばってあげてください。
小学生の場合:基礎力や環境が学習のカギになる
小学生が授業についていけない場合、次のような原因がよく見られます。特に低学年の頃は、親御さんとの関係性や信頼関係が学習進度の進展や後退に関係してしまいます。
• ひらがな・カタカナ・計算などの基礎があやふや
• 先生の話を集中して聞けない
• 黒板を書き写すのに時間がかかる
• 授業中に質問できず、分からないままにしてしまう
• 家庭学習の習慣が身についていない
また、オンライン授業やコロナ禍による影響で「わかったつもり」が増えたというケースもあります。
オンライン会議などで親御さんも経験していると思いますが、情報量が多く(必要でないことまで聞き取ってしまう等)、それだけで疲弊してしまうことが多いので、授業の受け方に工夫が必要になる場合もあります。
中学生の場合:学習内容の難しさと自己管理の難しさ
中学生になると、科目が細かく分かれ、教科書の内容も一気に難しくなります。小学生のうちは勉強が得意だった子ほど、一気にわからない所が増え、成績をガクッと落として自信を失ってしまう場合が多いです。
• 英語や数学など、勉強につながりがある教科が出てくる
(一度つまずくと、その先はどんどんわからなくなってしまう)
• 「分からない」と言いにくくなる
• 自分でスケジュールを管理する力が必要になるが、できない
• 授業のスピードが速くなる
• 思春期特有の精神的な不安や疲れがたまる
学習内容が難しくなってくると、学校や先生の説明スタイルと、お子さんの理解スタイルが合わず、それで理解が難しい場合もあります。学校の先生は代えられないし、そんな場合は自分に合った説明の仕方をyoutubeの動画などで探す必要があります。
発達特性が関係している場合も
授業についていけない原因の中には、発達障害やグレーゾーンの特性が関係していることもあります。
• 注意欠如(ADHD傾向):集中が続かず、聞き逃すことが多い
• 読み書きの困難(LD傾向):板書や教科書の読み取りが苦手
• 自閉スペクトラム傾向(ASD):曖昧な説明を理解しづらい
「本人は真剣なのに、どうしても噛み合わない」「家ではできるのに、学校ではできない」など、発達障害の子は勉強をさぼっているからという訳ではありません。
周囲の環境を調節してあげることで、理解できることが多いので、お子さんに合う学習スタイルを早めに試行錯誤しながら見つけていくことです。
授業についていけない子への親のサポート方法(小・中・発達障害共通)
お子さんの勉強のつまずきの原因がどんな理由であっても、親御さんのサポートでお子さんの状況は大きく変わります。
お子さん自身も授業についていけないことで「どうしよう。。」と怯えているので、できるだけ安心感をも持たせてあげるよう、サポートしてください。
• 「なんでできないの?」ではなく、「どこが難しかった?」と聞いてみる
• 教科ごとに「つまずいている内容」を一緒に振り返る
• 苦手な教科や単元は、毎日5分でいいのでやってみる
• お子さんが「安心して何でも話せる雰囲気」をつくる
• 学校の先生と連携し、見守りをお願いする
「ついていけてない=本人が悪い」という見方をせず、一緒に「どうすればやりやすくなるか」を探ってあげてください。
叱られたって勉強ができるようにはなりません。また「この間一緒に解いたじゃない」などと、お子さんを焦らせるような言動もやめましょう。
子ども自身が自分で考えることはもちろん必要なのですが、ますは意欲をもって取り組める環境が必要です。
親御さんができる具体的なサポート
「うちの子にはもっと、手取り足取りのサポートでないとダメ」と感じる親御さんも多いですよね。そんな方のために、できるだけ具体的なサポート方法を紹介しておきます。これをベースに、お子さんのやり方に合うよう工夫してあげてください。
親御さんが「わからないところは一緒に調べよう」というスタンスだと、子どもも安心して勉強に向き合えるようになります。
● 宿題やテスト勉強のスケジュールを一緒に立てる
→「夕方17時~18時は宿題、18~20時ご飯とお風呂、20時~21時はテスト勉強」といった毎日のスケジュールや時間割をお子さんと一緒に決めて、ホワイトボードや紙に書き出して見える場所に貼っておきましょう。
無理のないペース配分にするのが続けるコツです。また親御さんに許可を得て「今日はお休み」もありなど、ゆるいペースで始めてみてください。
●「今日は何を習ったの?」と毎日気軽に聞いてみる
→「へえ、今日は社会で戦国時代?どんな武将が出てきたの?」と興味を持って会話すると、子どもは話しやすくなります。特に歴史や国語などは会話のネタになりますから、楽しみながら想像力を広げていくとよいです。
また歴史や科学のマンガなど、子どもが喜んで食いついてくれそうなネタを仕込んでおくのもよいですね。
● 曜日や時間を決めて復習タイムをつくる
→ たとえば「火曜と木曜の夕食後は10分だけその日の復習タイム」など、短時間から習慣化すると効果的です。子どもが飽きないよう、終わったらおやつやご褒美シールをあげても◎。
習慣化は少しずつ、でもいずれは毎日を目指して、少しずつ曜日や時間を増やしながらコツコツと続けましょう。
● つまずいた単元は、動画やマンガ教材で楽しく補強する
→ 「九九が苦手ならYouTubeの歌動画」「歴史が難しいならマンガで読む」など、楽しみながら学べる教材を一緒に探してみましょう。市販の『学習まんが』や『学研・Z会の動画』もおすすめです。
● 成功体験を積ませる工夫をする
→ 子どもが「できた!」「わかった!」と感じられる場面を意識的につくりましょう。たとえば「10問中5問正解でもすごいね!」と努力を認めたり、「ここ、昨日より早くできたね」と具体的に褒めることが効果的です。簡単な問題からスタートし、徐々にステップアップしていくのもポイントです。
家庭学習の重要ポイント:勉強机の周りを整えよう!
机の上が散らかっていると気が散って集中しにくいです。
勉強の前に必要なもの(筆記用具・教科書・ノート)だけを出し、余計な物(おもちゃ・スマホなど)は片づけましょう。
「勉強前に2分だけお片づけ」を習慣にしてしまうと、お子さん自身がいずれは自分で出来るようになります。
授業についていけない子にNGな3つのこと
1. 「ちゃんと聞いていればわかるはず」と責めない
集中が続かない理由や、情報処理のスピードには個人差があります。責めることで自信をなくしてしまいます。
自信をなくしてしまったら、何をやっても上手くいかなくなってしまいます。
2. 焦らせすぎない
苦手意識が強くなると、勉強そのものが『大嫌い』になってしまいます。
ペースは本人に合わせながら、勉強の遅れを補習していきましょう。
ちょっと難しく感じるかもしれませんが、親子で一緒に笑いながら勉強していく形がベストです。
親御さんは深刻な雰囲気を作らないようにしてください。
3. できていないところばかりを指摘する
間違いを繰り返し指摘されると、「どうせ自分はダメ」と思い込んでしまいます。子どもが自己肯定感を下げてしまうのは、周囲の大人の心ない言葉が原因です。
小さな成功や努力を見つけて、認める声かけを心がけてください。
授業についていけないのは『よくあること』。大切なのは早めに気づいてあげること。
授業についていけない状態は、決して珍しいことではありません。小学生でも中学生でも、誰もがつまずきを経験することは、親御さんにも覚えがあるはずですし、発達の特性があれば、集団授業についていけないのは当たり前とも言えます。
大切なのは「どこで、なぜ、つまずいてしまったのか?」を一緒に見つけ、少しずつ解決していくこと。
叱るのではなく、「できたことを一緒に喜ぶ」「失敗しても受け止める」そんなふうに親御さんがかかわってあげれば、お子さんは困難にも立ち向かえる勇気を持つことができるようになります。
お子さんの「わからない」が「わかった!」に変わるのを見るのは、親御さんにも最高の喜びになるはずです。それまで、焦らず、寄り添いながらサポートしてあげてくださいね。






